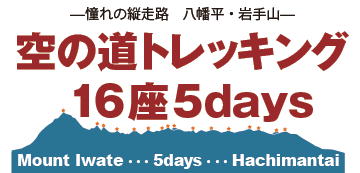神秘の『八幡平ドラゴンアイ』と
大展望の絶景を求め
残雪の八幡平を歩く
スノーシュートレッキング

雪の回廊が続く八幡平アスピーテライン、5月の八幡平はまだまだ雪の世界。
まばゆい雪原に日差しを浴びたアオモリトドマツ、ダケカンバの立木姿の素晴らしさに圧倒される。
雪を残した遠くの山々の大展望、雪解けの時期に姿を見せる神秘の自然現象
『八幡平ドラゴンアイ』も八幡平の残雪期の楽しみだ!
残雪トレッキングならではの圧巻の絶景がつづく!
● 県境登山口 ~ 八幡平ドラゴンアイ(鏡沼) ~ 八幡平頂上 ~ 八幡沼 ~ 源太森 ~ 県境登山口






展望の素晴らしいハイマツの稜線とアオモリトドマツ林の中を雄大な岩手山を望みながら安比・八幡平を経て裏岩手の縦走路を行く!

安比高原からの新道を、屋之棟岳を経て大展望の茶臼岳に向かう。源太森の大展望を楽しみ百花漣乱の八幡沼湿原の木道を歩き百名山八幡平の頂上を目指す。
- 行程
- 安比高原~屋之棟岳~茶臼岳~源太森~八幡沼~八幡平頂上~見返り峠

八幡平と岩手山を結ぶ縦走路。湿原のお花畑に圧倒される。アップダウンの樹林帯を出たり入ったり、常に左前方には岩手山を望む雄大なコース。
- 行程
- 畚登山口~畚岳~諸桧岳~険阻森~大深山荘~大深湿原~松川温泉

岩手山と八幡平の中間を位置し、高山植物、湿原、原生林と稜線歩きの醍醐味と素晴しさを堪能するコース。また、真っ赤に染まる本州一早い紅葉も三ッ石ならでは。秋もおすすめのコースの一つである。
- 行程
- 松川温泉~源太ヶ岳~大深岳~小畚岳~三ッ石山~三ッ石山荘~松川温泉

岩手山登山コースの中でも最も変化が多く原生林、湿原の花、岩稜を楽しめる。本命の岩稜・鬼ヶ城の稜線は目の覚める展望とお花畑の花々が迎えてくれる。
- 行程
- 松川温泉~姥倉~黒倉~鬼ヶ城~岩手山八合目避難小屋(泊)


天空の路を登り岩手山の頂上へ。360度の大展望は感動の一言。翌朝、山頂付近から見る日の出。お鉢のコマクサと八ッ目湿原の花々に感動し鬼ヶ城の素晴らしい岩稜の尾根を眺め切通しから姥倉、大松倉を経て松川温泉に下る。
- 行程
- 八合目避難小屋~不動平~岩手山頂上~平笠不動小屋~八ッ目湿原分岐~切通し~姥倉~大松蔵~三ッ石山荘~松川温泉
のどかな草原と赤い屋根の山荘が牧歌ムードを盛り上げる。北峰、南峰の二つのピークは絶好の展望台だ。

- 難易度
- ★★☆☆☆
- 山行時間
- 4.5時間 / 歩行距離 8km
- 行程
- 田代平登山口~七時雨山頂(北峰、南峰)~登山口
ブナ原生林から火山地獄と変化にとんだコース。秘湯から秘湯への贅沢な山旅。

- 難易度
- ★★★☆☆
- 山行時間
- 6時間 / 歩行距離 8km
- 行程
- 御生掛温泉~べご谷地~湯ノ沢~焼山山荘~焼山山頂~毛せん峠~御生掛温泉
岩手山と八幡平の中間にあり、お花畑、湿原、原生林と東北の山ならではの奥深さを感じさせるコース。素晴らしい稜線歩きは圧巻。

- 難易度
- ★★★☆☆
- 山行時間
- 8時間 / 歩行距離 12km
- 行程
- 松川温泉~源太ヶ岳~大深岳~小畚岳~三ッ石山~三ッ石山荘~松川温泉
八幡平と岩手山を結ぶ縦走路。起伏のある稜線からは常に壮大な岩手山の展望が楽しめる。また四季折々で素晴らしい高山植物、紅葉に驚かされる。

- 難易度
- ★★★☆☆
- 山行時間
- 8時間 / 歩行距離 12km
- 行程
- 畚岳登山口~諸桧岳~険阻森~大深山荘~源太ヶ岳~松川温泉
岩手山登山コースの中で最も変化が多く原生林、滝、沢、湿原を楽しめる。特に大地獄谷の荒涼とした風景は一見の価値がある。

- 難易度
- ★★★★☆
- 山行時間
- 9時間 / 歩行距離 14km
- 行程
- 七滝登山口~大地獄谷~不動平~岩手山頂上~平笠不動小屋~お花畑~七滝
火山複雑地形の山岳美とチングルマ、コマクサを始めとした高山植物の豊富さでは東北屈指の人気の山。

- 難易度
- ★★★☆☆
- 山行時間
- 7時間 / 歩行距離 10.5km
- 行程
- 国見温泉~横長根~ムーミン谷~阿弥陀池~男女岳~横岳~大焼砂~国見温泉
ハヤチネウスユキソウなど高山植物の宝庫として全国に知られる花の名山。岩稜の秀峰が印象的である。(シャトルバス料金別途)

- 難易度
- ★★★☆☆
- 山行時間
- 6時間 / 歩行距離 6.5km
- 行程
- 小田越登山口~御金蔵~分岐~早池峰山頂上~御金蔵~小田越
樹林帯を抜け花崗岩が積み重なった巨岩の山頂からは岩手山はもちろん早池峰山、秋田駒など360度の大展望が楽しめる。

- 難易度
- ★★☆☆☆
- 山行時間
- 4時間 / 歩行距離4.5km
- 行程
- 一本杉登山口~ざんげ坂~姫神山頂上~こわ坂コース~登山口
- 【ウェア】
- 長袖のもので速乾性のものが望ましく、インナーは、機能性の良いものを、アウターは防風性、防水性、保温性の高いものを選びましょう。
- 【ディパック】
- 日帰りの場合は20リットル~30リットル程度の背負いやすいものがおすすめです。
- 【水筒】
- 1リットル程度のものを必ず持ちましょう。
- 【手袋】
- 防水性と保温力の高いものを選びましょう。
- 【帽子】
- 直射日光や寒さ、木の枝等障害から頭を守ります。できればツバのあるものを選び必ず着用しましょう。
- 【スパッツ】
- 雨や雪・砂などの進入を防ぎます。あると便利な一品です。
- 【ストック】
- 体重の分散とバランスの保持等を目的とします。
- 【防寒具・靴下】
- フリースやセータ、厚手の靴下等防水性に優れ保温を確保できるものを用意しましょう。また、タオル・ビニール袋等もあれば便利です。
- 【筆記用具・救急用具】
- 以外と役に立つのが筆記用具。ちょっとしたスケッチや事柄をメモしておくだけで、旅がさらに楽しい思い出となります。
- 【シューズ】
- 高度の高い山や道の悪い山などの場合は、革製のものが望ましく、比較的道の良いところは軽登山靴でOKです。できるだけ自分の足に馴染んだものがベターです。